このページでは、
ロゴジェンモデルの音響分析について
説明します。
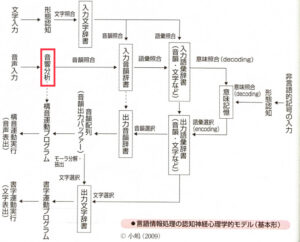
異同弁別という言葉が多く出てきます。
異同弁別とは、
2つの刺激が同じか異なるかを
答える課題です。
例)
/ta/と/ta/ :同じ(○)
/ta/と/ka/ :異なる(✖️)
✔︎ 音響分析とは、
語音の音色を聴き取る能力
✔︎ 音響分析障害は
聴力検査は良好だが、
単音の異動弁別ができない場合に疑う
✔︎ ウェルニッケ失語に合併しやすい
✔︎ 聴く構えができてから、
聴覚的課題をしてもよい
音響分析とは

語音の音色を正しく聴き取る能力をいう。
小嶋は、語音認知には、
弁別と認知の2段階があると述べており、
音響分析は、「弁別」の段階である。
つまり、
/ta/と/ka/が同じか否かを
聴覚的に判断するのが
音響分析能力である。
なお、次のレベルの音韻照合にて、
/ta/が/ta/であると認知される。
音響分析障害とは

音響分析障害では、
純音聴力検査は良好でで
環境音の聞き分けも可能である。
しかし、
語音を聞き分けることができなくなる。
ウェルニッケ失語に
合併しやすいと言われている。
例1)
/ta/と/ka/を音声提示されたときに、
同じ音だと判断してしまう。
例2)
/ma/と/ma/を音声提示されたときに
違う音だと感じてしまう。
検査法

✔︎純音聴力検査にて、聴力が保たれている
✔︎SLTAの口頭命令、文の復唱の得点が
良ければ良好の可能性大。
✔︎SLTAの仮名の理解が全問正答であれば、良好の可能性大。
誤答でも、障害だとは言い切れない。
(音韻選択の障害が関与しているかも)
✔︎詳しくは
SALA失語症検査の聴覚性異動弁別で判断
✔︎単音の復唱で一定の評価は可能
良好ならば、音響分析は良い可能性あり
不良でも障害があるとは言い切れない。
(音韻選択障害が関与しているかも)
音響分析障害の訓練法

文字を用いた意味セラピー
音響分析から障害されている場合
聴覚刺激の訓練は拒否につながりやすい。
そのため、
文字や絵を用いた意味セラピーを
優先的に行う。
会話場面で、患者様が
「え?何?」という反応が増えてきたら、
聴く構えができてきたと考え、
聴覚刺激での訓練を開始していく。
詳しく知りたい方は、こちらから
楽器の音色の弁別
語音の「音色」の弁別が苦手ならば
楽器の音色の弁別能力を先に伸ばそう!
という課題
レベル①
異なる楽器を用いた異同弁別
例)
ピアノの音、ギターの音
レベル②
同じ楽器を用いて音階を変えての異動弁別
例)
ピアノ「ド」、ピアノ「ソ」の○✖︎
段階的な単音の異動弁別
異同弁別のレベルを徐々に上げていき、
単音の弁別能力の向上を目指す訓練法
レベル①
母音と子音どちらも異なる音で○✖︎
/ka/と/te/
レベル②
母音のみ異なる音で○✖︎
/ka/と/ke/
レベル③
子音のみ異なる音で○✖︎
/ka/と/ta/
おわりに
今回は音響分析についての説明でした。
ウェルニッケ失語に合併しやすい
音響分析障害。
聴覚的理解が不良なので、
聴覚刺激での訓練を行いたいのが本音。
しかし、そこは慌てずに
患者様の聴く構えができてから行う方法も
あります。
頭のスミに入れてくださればと思います。
なお、本記事は
下記の書籍を参考にさせていただきました。
\まずはここから/
\なるほど失語症との親和性抜群/
\症例や訓練法が多彩/
ロゴジェンモデルをもとにした
デジタル訓練教材を販売しています。
興味がある方はこちらからどうぞ
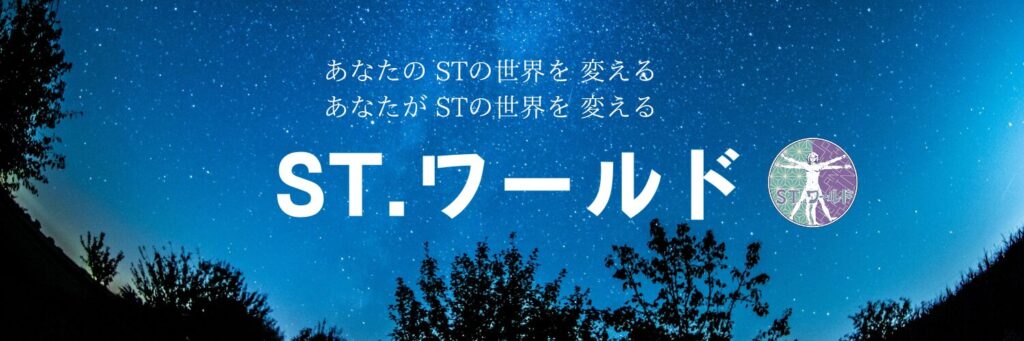


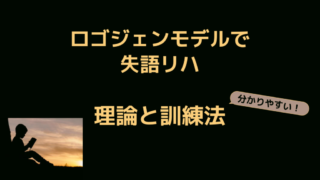

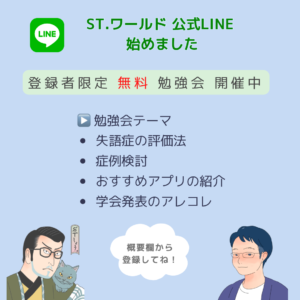
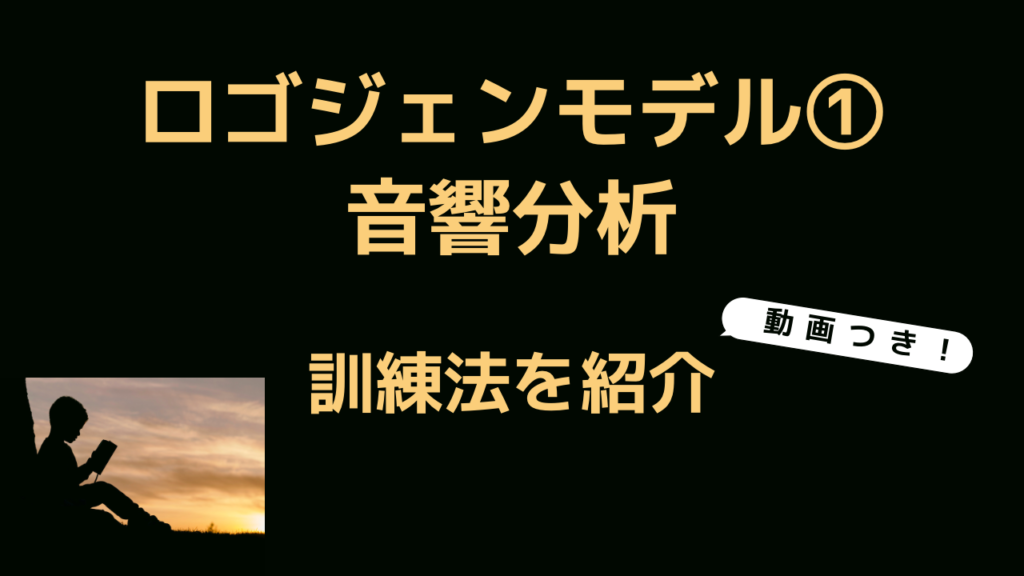

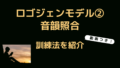
コメント