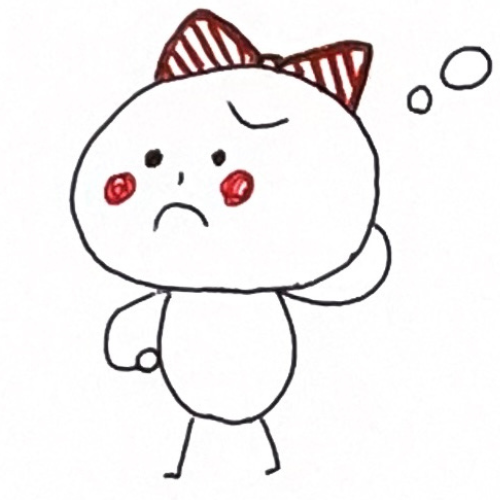
ワーキングメモリの機能訓練ってプリントでしづらいよね

ワーキングメモリ課題はアプリが大活躍だね!

使えるアプリを教えて!
プリントでワーキングメモリの機能訓練を
するの難しくないですか?
脳卒中後遺症の患者様に多い
ワーキングメモリの低下
しかし、プリント課題では機能訓練が難しい(気がする)
本記事では、そんな悩みを解決するために、
日頃からアプリサーフィンをしまくっている私が、
ワーキングメモリのアプリを紹介します。
本記事を読めば、
ワーキングメモリシステムの概要と
機能訓練に使えるアプリが分かり、
臨床に役立てれるかと思います。
アプリを使用した訓練で、
少しでも患者さんが楽しめるリハビリになればと思います。
結論①:ワーキングメモリは会社と似ている
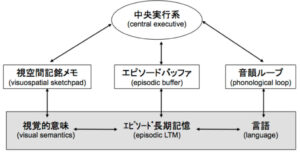
上司:中央実行系
部下:
・視空間スケッチパッド
→視覚系の短時間の記憶と処理を行う
・エピソードバッファ
→複数モダリティの記憶と処理を行う
・音韻ループ
→聴覚系の短時間の記憶と処理と行う
普段は部下が働き、
上司は表に出てこない。
非日常的なことが起きた際に上司が働き
どの部下が中心となって対応するか決定
ワーキングメモリシステムの
詳しい内容を知りたい方はこちら⬇️
結論②:ワーキングメモリに使えるアプリ3種
本記事で紹介しているアプリは
下記の4つです
聴覚性ワーキングメモリを鍛える
デジタル教材


Lumosity: 毎日の脳トレゲーム
※一部有料






毎日の脳トレーニング






脳トレ - 記憶ゲーム




音韻ループと視空間スケッチパッドを鍛えるゲーム
音韻ループを鍛えるゲーム


聴覚性ワーキングメモリ課題(自作)
小学生からできる
音声を聴きながら解く
クロスワード課題
【手順】
❶パワーポイントを開始
❷音声を聴く
❸正しく聴きクロスワードを解く
Lumosity:スーツケースシャッフル
ホテルマンがbagを配る
【手順】
❶bagの色と個数を覚える
❷客の要望するbagが手元あれば渡す
❸要望するbagがなければ、渡さない
※私は青○個、赤○個と音で覚えるため
音韻ループアプリに入れました
レベルが上がるにつれて、
覚えるバックの個数が増えていき、
複雑化していきます。


Lumosity: 毎日の脳トレゲーム
※一部有料




Lumosity:黒板チャレンジ
2つの式を暗算し、大きい方を選ぶ
・答えが同じ場合は「同じ」を選択する
2つの式を計算が出現する。
答えを把持しながら
他方の計算もするゲーム
序盤は簡単ですが、
後半は( )付き式も出てきます


Lumosity: 毎日の脳トレゲーム
※一部有料




音韻ループを鍛えるおすすめ教材
小学生対象に作られた教材だが、
脳卒中後遺症のある患者様も使える内容
対象者が短文〜長文の概要を
理解するゲーム感覚の課題が
多数収録されている
視空間スケッチパッドを鍛えるゲーム


毎日脳トレ:シルエットボックス
箱の中を出入りする動物を見て、
最後に残った1匹を選ぶ
※イラストではなく名前で考える方は
音韻ループに入るかも
シルエットの動物の行き来が
とっても可愛いゲームです


毎日の脳トレーニング




脳トレ -記憶ゲーム-:クッキングピザ
ピザの材料と個数を覚えて、再現する
※具材の名前と個数を音声で覚える方は
音韻ループのゲームになるかも


脳トレ -記憶ゲーム-




Lumosity:空まで届け
一瞬出る数字を覚えて、
小さい順にタップする
難易度が上がるにつれて、
個数が増えたり、広範囲に数字が出現します


Lumosity: 毎日の脳トレゲーム
※一部有料




Lumosity:鯉の池
動き回る鯉に1個/匹ずつエサを与える
どの鯉に餌をあげたか覚えつつ、
次の鯉に餌を与える
鯉が動き回るのが、いじらしい


Lumosity: 毎日の脳トレゲーム
※一部有料




Lumosity:ピンボール
ピンの位置を覚えて、ボールがどこへ
進むかを当てる


Lumosity: 毎日の脳トレゲーム
※一部有料




まとめ
今回は、ワーキングメモリの概要と
アプリを紹介しました。
中央実行系を鍛えるアプリはないの?
と感じた方がいると思います
先述したように、
日常的な場面では部下が活躍し
中央実行系は非日常的場面に出くわした時に出現します
そのため、
セラピストが意図的に
非日常を演出しなければ鍛えられない
と思われます
そう考えるのであれば、
ご年配の方にiPadでアプリに触れていただくのも、
中央実行系が働くのですかね…笑
私には、分かりません
一つ言えるとすれば、
視空間スケッチパッド、音韻ループを鍛えることで、
中央実行系の円滑な働きに繋がるので、
両者を鍛えることは、ワーキングメモリシステムを鍛えることに
つながるのではないかと思います
ここまで読んでいただき、
ありがとうございました。
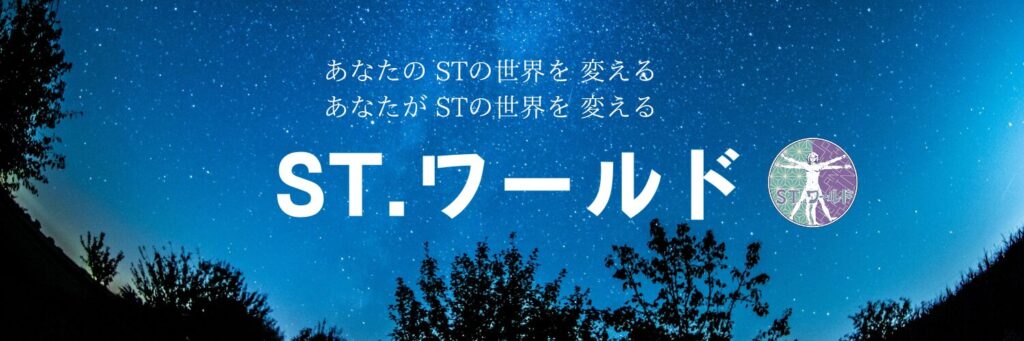


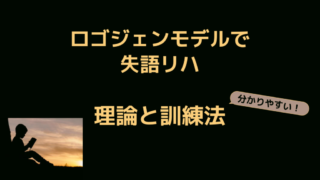

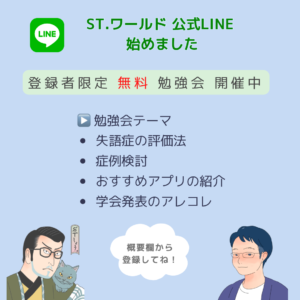
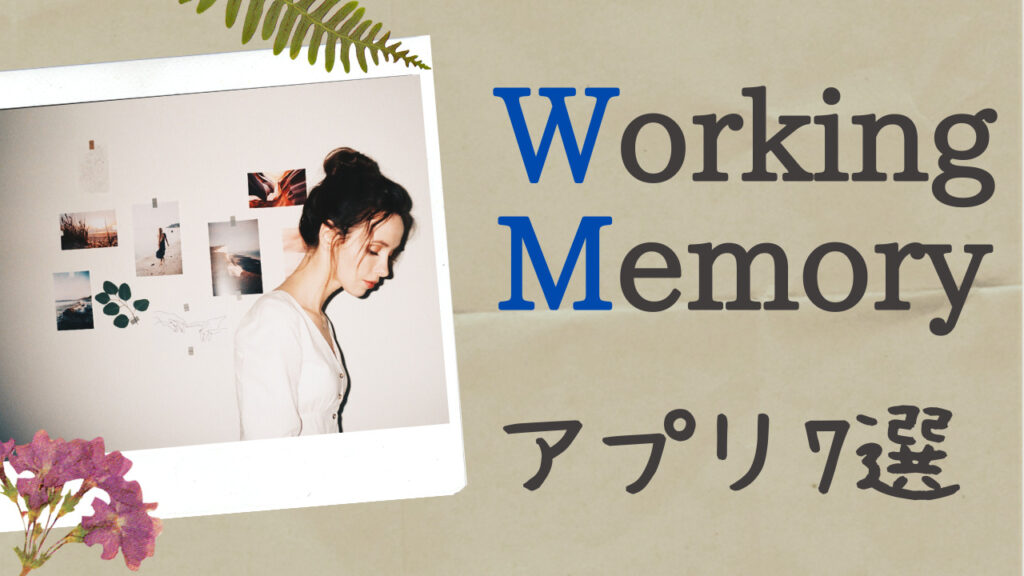
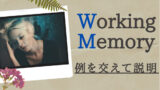
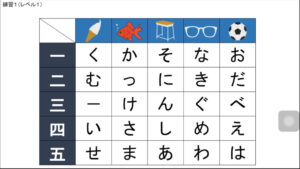

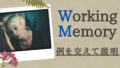

コメント